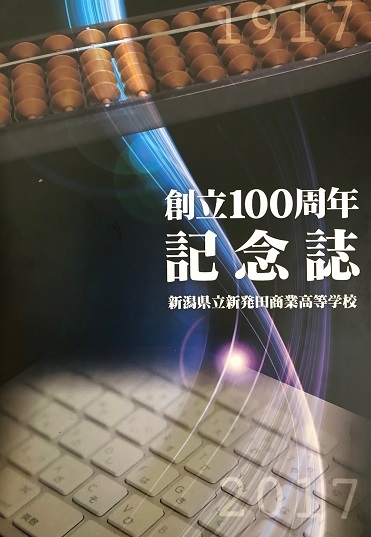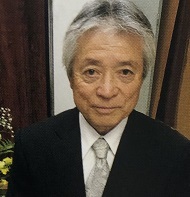〇記念式典
平成29年11月11日(土)
在校生を含め、700名を超える出席者が見つめる中、記念式典が盛大に挙行されました。

〇記念祝賀会 平成29年11月11日(土)
○100周年記念体育祭 「100」人文字撮影(ドローンによる撮影)

○教育施設の充実 電子黒板9台設置(教室棟)
○記念タオルの制作(生徒デザイン)
○記念講演 「オリンピックからエベレストへ」
プロスキーヤー・医学博士 三浦豪太 氏
リレハンメル五輪の出場権獲得

モーグルというのは日本人で活躍している選手も現在で結構多いですし、20年前のこのリレハンメルの時でも世界ランキング20位以内に日本人が3人いたんですね。20位以内に3人というのは考えられないぐらいすごくて、テニスも錦織選手くらいですよね。この3人でリレハンメルオリンピックの出場枠を争わなければいけないという状況になりました。
リレハンメルオリンピックの枠は、日本ではその当時1人しか出さないと連盟が言っていました。
最後、その試合を決めるのは北米戦というアメリカとカナダのワールドカップの大会で決めようということになりました。ワールドカップというのは、オリンピックに準ずるような世界トップの選手たちが出てくる大会で、その中で一番いい成績を残した選手が選ばれることになりました。
でも、ワールドカップって結構レベルが高いから、ちょっとしたミスでも本当に10番ぐらい変わるんですね。他の日本人選手2人は、36,37番、私が46番ぐらいでした。どんぐりの背比べのような状況だったんです。僕もミスをしていて、オリンピックに行くまでは決定打にならなかったんです。
そうすると次のオリンピックの決め手になるのは何かというと、ブリッケンリッジというアメリカにある大会だったんです。でも僕はその第一試合で大けがをしてしまいました。着地の瞬間にふくらはぎをスキー靴に強打してしまいました。脛骨と腓骨の間の筋肉の膜が破れてしまって、まるで象の足のように太ももよりも下肢の方が太くなるくらいまで腫れ上がりました。そうなった状態でリレハンメルオリンピックの最後の選考会に滑らなければならなくなったのです。
大会までの1週間の公式練習すら滑れず、毎日病院通いでした。一本も滑れず、会場から足を引きずりながら宿に帰るとき、日本の両親に電話することにしました。変に期待をさせたくなかったのです。
最初に電話に出た母は、「痛い思いをしてまで滑る必要はないから、日本に帰ってきたらいいわ」と言いました。ところが電話を無理やり代わった父が、「足の調子はどうだ?折れているのか」と聞いてきました。いや、折れてはいないけれど、すごく腫れているんだと答えると、父は「おお、折れていないなら大丈夫だ。やけのやんぱちでどうにかしろ」と言いました。「やけのやんぱち」は青森の方言だと思いますが、そう言われて僕もカッとなって、電話器をたたきつけるように電話を切りました。
その直後、僕は「なんだ、親父は人のことも考えないで」と思いました。しかし、ふと気づくと足を普通について歩いているのです。さっきまで引いていた足を地面に付けているのです。怒りで痛みを忘れてしまったのです。これならなんとかなるかもしれないと思い始めました。その後、スーパーへ行って、のこぎりを買いました。スキー靴のアッパー部分をノコギリで切り、なんとか足を入れることにしました。さらにテーピングをぐるぐる巻きにして、なんとか足を固定しました。これで一本だけ滑ってみようと考えたのです。
次の日の大会当日、当然ながら本来の力は出せないけれど、その状態でもなんとか一本滑ることに決めました。ぐらぐらするスキー靴で無難に滑ることを心がけました。ジャンプも高くなく、スピードもほとんど出ませんでした。結果は60人中27位でした。他の日本人選手は普通に滑れれば10位以内に入ると思われた選手でした。ところが最初に飛んだ日本人選手が、ジャンプの着地でバランスを崩して、コントロールゲートの外側を滑ってしまいました。ゲートの外を滑ってしまうことは、途中で棄権を意味するのです。プレオリンピックで優勝していた選手が途中で棄権する状況になってしまったのです。2人目の日本人選手もかなりの実力者でした。第1エア、同じところでコースアウトしてしまったのです。無難に滑った私が3人の中で順位が1番上になってしまったのでした。
ということで、リレハンメルオリンピックに出られることになりました。この経験から私が言いたいのは、三浦家の家訓であるのですが、「できない理由よりできる理由を考えよう」ということです。この時も足が痛いとか折れていないとか、そういったことを考えていれば勝負は始まらなかったのです。
高校生に伝えたいこと
「心の壁」というスポーツ心理学において使われている言葉があります。この「心の壁」は実は語源がありまして、1950年代のイギリスで行われていた陸上競技の中に「1マイル走」という種目があったのです。しかし、どんなに頑張っても人類は4分10秒を切ることができませんでした。
4分という壁を越えることはできないだろう。できてもせいぜい4分8秒ぐらいだ、4分の壁を越えることは不可能だと言われていました。それは当時のお医者さんやスポーツ生理学者、コーチもみんな言っていて、4分を切ったらお前は死んでしまう、足の骨が折れてしまうと警告していたのです。
この記録に挑戦しようと考えたのが、当時のオックスフォード大学のロジャー・バニスターさんという陸上選手でした。オックスフォード大学の医大生ですね。彼はどういうことをしたかというと、逆転の発想をしたのです。必ず4分内に収まるようなスピードで1周ずつ回る。だから4分を切るということは、1周を1分で回ることになるのです。この距離をもっと伸ばしていこうではないかと考えるわけです。トレーニングを重ねて半年後、ついに3分59秒という記録を出したのです。これは当然、並走もつけているし、自分のコンディションに合わせて作った記録なので、公式記録にはならなかったのです。でも大きなニュースになったのです。ついに4分を切るというニュースが大きく報じられました。もっとすごいことが起きたのは、次の年です。なんと、その後1年以内に4分の記録を切った人が18人も現れました。それまで4分を切ったら死んでしまうと言われていたその記録を、1人の選手が可能性を示すだけで、次々と破られるという事象が起きたのです。
皆さんの場合、まだこれからたくさんの可能性があります。目の前にはたくさんのハードルを越えなければならず、たくさんの扉を開けていかなければなりません。だから、目の前の扉しか見えないかもしれなし、目の前の壁しか見えないかもしれません。この壁が積み上がったらこんな壁登れないと思うかもしれない。でも、その壁は自分の心の中で作っている壁です。もし何か迷ったら、80歳でエベレストに登っている三浦雄一郎さんの登頂シーンを思い浮かべながら、こんな人もいるんだなと思って、これからも頑張ってください。
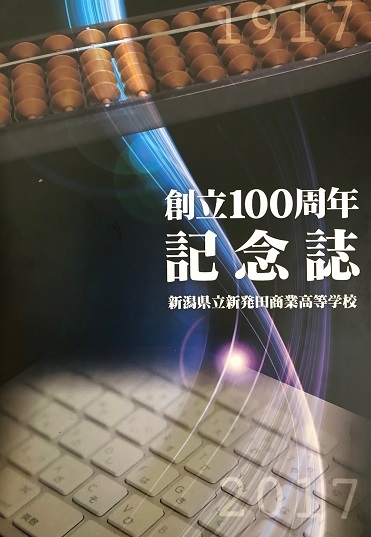
創立100周年記念誌に掲載されている記事を抜粋し紹介させていただきます。
記念誌出版のご挨拶
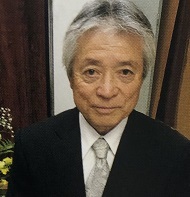
県立新発田商業高等学校創立100周年、誠におめでとうございます。記念誌出版に際し、同窓会を代表してご挨拶させていただきます。
100周年、なんという響きと重さのある言葉でしょうか。大正6年に新発田町立商業学校としてスタートし、平成29年に100周年を迎えることになりました。関係各位におかれましては、誠におめでとうございます。記念誌出版に際し、ご挨拶申し上げることになったのは、誠に名誉なことです。
さて、大正6年は西暦1917年で、第一次世界大戦が始まった年です。奇しくも現在、朝鮮半島では緊張状態が続いていますが、100年を経て今も続く歴史の愚かさを感じざるを得ません。
その後、1948年に学制改革で土木科、建築科、商業科を置き、新潟県立新発田商工高校となりました。この年を前後して生まれた人たちがベビーブーマー世代として戦後の日本の高度経済成長を支えていくことになります。そして、1983年に工業科を分離し、県立新発田商業高等学校となり、今日に至っています。
1983年は、インターネットが誕生した年で、任天堂からファミコンが発売され、今日のゲーム時代の基礎となりました。1980年代は俗にバブルと言われた時代です。商業高校としてこの地に移ってから、今年で35年になりますが、たった35年の歳月にもバブル期、バブル倒壊期、就職難の時代と幾多の大きな時代の変化がありました。こうしてみますと、100年というのは括りとしては聞こえの良い単位ですが、大きな浮き沈みがあり、まさに学校は荒波の中を進む船のようでもあります。100周年というのは、まさに100年の航海と言い換えても良いでしょう。
100年に渡り、学び舎という船で多くの卒業生を世に送り出し、日本の歴史の一端を担ってきたことになります。知識という船に乗って、知恵というオールを漕ぎ、人生という海を渡る。しかし、時代という荒波は予想不可能に近く、幾多の困難が立ちはだかるわけですが、100周年に渡り漕ぎ続けてきた同窓生に対して感謝と敬意を持って、100周年の時を祝福させていただきたいと思います。
そして在校生の皆さん、迫りくる荒波に恐れ慄いては、未来は開けません。時代の波に負けない屈強な精神や肉体を持ち、知識を得、知恵を働かせることで未来は開けてきます。この先、100年の子どもたちの可能性と同窓生の航海の行く末の希望を願い、100周年の記念誌出版のお祝いのご挨拶とさせていただきます。おめでとうございます。
同窓会長 椎谷和男(商工第20回卒)
玲瓏高き芝商に入学 嶋谷次郎八(商工第10回卒)
今から60年も前の話です。高校受験は芝商と決まっておりましたが、受検志望校を選択する頃、中学の担任から呼び出されました。別に校則に違反した覚えはないのに・・・と教務室に入ると、「君は芝商を受験希望だが、今の成績では入学は難しい・・・もっとしっかり勉強しろ!!」と喝を入れられました。そして昭和32年4月、下越きっての名門校、新発田商工に入学することができました。前年昭和31年4月15日には白山、新発田間の白新線が全線開通しておりました。男子45人、女子10人、55人のクラスメートは、汽車通学35人、自転車通学4人、下宿1人、市内15人で編成され、昭和35年(1960年)3月の卒業まで変わることはありませんでした。
入学早々、「爛漫として咲き匂ふ・・・」と唄われた長堤10里の桜咲く加治川の土手で、3年生から気合を掛けられ、校歌、応援歌を教わった事が懐かしく思い出されます。クラスでは授業のやり方を巡って国語の先生と激論する者がいたり、汽車通学の下級生の喫煙を注意して殴られた同級生の仇討!!として下級生5人を殴り倒して停学処分を受けた猛者もいました。青春時代の3年間、ずっと机を並べていると、55人が兄弟のような存在だと思う時もありました。
卒業後、初めて三和銀行へ入社する者、新潟大学を経て大学教授になる者、衆議院議員となって国会の赤絨毯を踏む者、水原を拠点に東京駅八重洲口でビアホールや銀座で料理店を経営する者。まさしく多士済々の面々です。既に数名は物故となりましたが、卒業以来、1月第2日曜日正午開会と決めて、新年と健康を祝いつつ、60年前の芝商生にかえって旧交を温める、1年で最も大切な一日となっております。
100周年に寄せて 北海道大学情報科学研究科 教授 平田 拓(商高第1回卒)
創立100周年おめでとうございます。私は現在の校舎に移転した後、最初の3年生として1984年3月に卒業しました。その後、学部、修士課程、博士課程と別々の大学で学び、1993年に東京工業大学で博士号を取得しました。
最近は母校でも進学する生徒が多いようですが、当時の卒業生としては、大変稀なルートを辿りました。高校3年生の10月くらいになり、ようやく大学を受験することを決めました。そのため、受験勉強らしい勉強はしておらず、推薦入試で大学に進学することにしました。大学に入学すると、各地の進学校から来た学生が知っていること(例えば数学の解法)を知らないため、勉学の面で大きなハンディがありました。しかし、好きなことは多少の苦労があっても続けられるため、3年を過ぎると進学校出身の学生にも負けないようになりました。
ここでの私の教訓は、十分に勉強せずに大学に進学してしまい、後方からのスタートであっても、自分の目標に近づくためにやり続ければ、長い間に大きな違いが出る、ということです。
勉強は先人が築いた知識を理解して使うことですが、研究は新しい知識を生み出すことです。この2つはまったく別の能力が必要です。研究は誰もやっていない新しいことに取り組むため、常に失敗します。成功するまでやり続けることができる人にだけ、成功のチャンスがあります。2008年に山形大学から北海道大学へ異動し、現在は磁気共鳴イメージングの研究をしています。北海道大学は札幌農学校の初代教頭・クラーク博士の「少年よ、大志を抱け」で有名な大学です。北海道大学の教授として研究や教育を仕事にすることは、高校生の頃には夢にも思いませんでした。大志を持っていたわけではありませんが、色々な成り行きで現在に至りました。在校生の皆さんには、狭いところに壁を作らず、広い気持ちで次の100年を築いてもらうことを心から望みます。
創立100周年において 最年少税理士資格取得 大矢さよ子(商高第14回卒)
新発田商業高等学校の創立100周年おめでとうございます。様々なものが変化していく世の中で、100年もの間学校として存続していることを素晴らしく思います。
私は23年前、新発田商業高校の商業科に入学しました。高校生活3年間における出来事がきっかけとなり、現在は会計事務所に勤務しています。仕事上、さまざまな業種の方と話をします。その中で出身高校を訪ねられますが、高校名を答えると新発田商業高校の評価の高さに驚かされます。
高校に入学する前、新発田商業高校についての意見を聞くと口を揃えたかのように、真面目で優秀な学校という言葉が返ってきます。そのイメージを変える出来事が入学した年に起こりました。「天才たけしの元気が出るテレビ」に新発田商業高校が出演したのです。放送後は面白い学校と言われるようになったのですが、時の経過とともに聞かれなくなったのは、寂しいところです。
卒業後、新聞や県内ニュースなどで新発田商業高校の話題を見ることがあります。主に運動部の地区大会の結果、事業の一環として行われている活動の紹介で、話題が出る度にその時々における在校生の部活、授業に対する頑張りを感じます。また、その活動内容も現実の経済活動に近いものであり、社会人になったときに即戦力となると感じました。前々からの評価に加えて、外部への情報発信により、私が受けた評価の高さにつながっていたのです。商業高校生として充実した高校生活が送れるよう陰ながら応援しております。
日本一になる 長野かがやき国体少年女子第1位
松尾久留美(旧姓渡邉 商高第25回卒)
「日本一になる」という目標を心に決め、伝統ある新発田商業高等学校スキー部に入部したのは、今から約10年前のことです。
スキー部には、兄と弟、小さい頃から一緒にスキーをしていた先輩や後輩ばかりで、男女ともに仲が良いというのがこの部の伝統でした。また、部員はスキー歴0日の者から全国大会出場者まで幅広く、個性的で常に活気があり、明るいチームでした。しかし、ひとたび部活が始まると、緊張感のある雰囲気や礼儀正しい言葉遣い、1分1秒を無駄にしない素早い行動、魂のこもった声が響き、全員が全力で同じ方向を向いて練習を行っている団結力のあるチームだと実感しました。このとき、私はこのチームは日本一の練習をしていると感じ、この人たちと一緒に強くなりたいと思ったのを今でも覚えています。
時には失敗から学ぶこともありました。私は高校1年生の終わりにスキーで転倒し、左膝の手術を受けました。その後、表彰式で膝の痛みを言い訳にして、同じ新潟県の先輩たちの表彰式に出なかったことがありました。その時、先生から「怪我のせいにするのは選手失格だ」と厳しく指導されました。スキー部顧問の皆川先生は情熱の塊、練習の鬼。しかし厳しさの中にも愛情がありました。「スキー馬鹿になるな。良いスキーヤーの前に良い社会人であれ。」と常に教えていただきました。ご指導のおかげで、選手としての未熟さを痛感するとともに、視野が広がり、礼儀を重んじることの大切さを学ぶことができました。
国民体育大会で優勝できたのは、最高の指導者や部員、仲間との出会いや家族、友人の支えがあったからです。3年間を通して、人としての成長をさせてもらった時だったと感謝しております。新発田商業高等学校のさらなる発展をお祈り申し上げます。
都大路を目指した戦いの日々 旧職員 陸上部顧問 山崎かおる
新発田商業高校には、昭和63年から平成13年までの14年間お世話になりました。2年目の平成元年に全国高等学校女子駅伝大会がスタートし、第一回大会から合計9回出場しました。
第1回43位 第2回38位 第3回44位 第5回48位(記念大会では58チーム参加)
第6回目46位 第8回43位 第9回21位 第10回29位 第11回28位
何度全国に挑戦しても成績は振るわず、都大路を目指してくる生徒の気持ちとの狭間で苦しい時期もありました。しかし、第8回大会を43位で終えた時、生徒に来年の目標は20位と話し、第99回大会では奇跡が起こりました。レース当日の朝、練習の前に宿舎前の西本願寺へ生徒とお参りに行きました。私の前に生徒全員が並び、手を合わせた瞬間、私にとっての仏様は目の前にいる生徒なのだと思えて涙が溢れて止まりませんでした。これから勝負に向かう選手に悟られまいと、まだ夜が明ける前の薄暗い境内でそっとサングラスをかけました。そして本番、3000mでは、平均タイム40位のチームが1区を16位で滑り出し、すべての区間を完璧な走りで襷をつなぎ、21位でフィニッシュしました。この奇跡が起こったのは、新発田商業高校が創立80周年、さらに新発田市制50周年という節目の年であったことにも感慨深いものを感じます。この結果は県の最高順位、最高記録として、未だ破られていません。
駅伝を通じて、選手と保護者の方々、学校関係者の皆さま、OB会の皆さま、そして地域の方々からたくさんのご協力を賜りました。県大会で敗れたことや全国で何度も悔しい思いをしたことすべてを含めて、新発田商業高校でのご縁は私のかけがえのない宝物です。本当にありがとうございました。私にとっての心の母校である新発田商業高校が、これからもますます発展しますよう心よりお祈りいたします。
商業クラブ7年間の取り組み 現職員 佐藤 匠(商高第5回卒)
平成23年4月に着任し、最大の難関が「商業クラブ」でした。「商業クラブって何?」何をどうしてよいか分からない状態でした。当時の部員は2人、それも他の部活動との兼部のため、放課後は誰もいませんでした。翌年から6年連続で全国大会に出場した生徒たちは、頑張って取り組んだと思います。7年間のテーマと取り組み内容は、下記のとおりです。
平成26年度「パワーリーフの知名度アップを目指した取り組み」は、新聞や雑誌に掲載され、さらにテレビ局から一日密着取材を受け、生放送にも出演しました。何を話すのか、ハラハラしました。
また、JA主催の大会にも出場し、約80校が参加した東日本大会予選を勝ち抜き、仙台市で行われた東日本大会に出場しました。出場校のほとんどが農業高校であり、商業高校は本校だけでした。半分諦めて気軽に臨んだことが幸いし、優勝することができ全国大会に出場することになりました。
この年は商業クラブの全国大会が11月18日から21日まで北海道で行われ、JA主催の全国大会が22日から23日に東京で行われました。北海道での全国大会は20日の発表だったので、終了後すぐにJA主催の全国大会の練習をホテルで始めました。観光にも行かず、美味しいものも食べず、夜遅くまでホテルで練習をしていました。22日に新潟空港に到着し、そのまま新幹線で東京へ向かいました。ともに全国大会入賞はできませんでしたが、部長だった生徒が「疲れたけど、やりきった3年間楽しかった。悔いはありません。」と、とても清々しい表情をしていました。彼女が1年生の時に言った「絶対負けません。三連覇を目指します。」という言葉が新聞に掲載されたことが、全ての始まりでした。
地域活性化を目指し、ここまで活動を続けることができたのは、商業クラブを温かく見守ってくださった先生方や地域の方々、保護者の皆さまのおかげです。この場を借りて御礼申し上げます。
<研究テーマ>
| 平成23年度 |
「原点回帰 ~これからの芝商に求められていること~」
本校の過去の取り組みと地域住民から求められていること、今後の展望についての調査 |
| 平成24年度 全国大会出場 徳島県 |
「東北商品と芝商商品の販売で地域活性化!~Win-Winの実現とソーシャルマーケティングを目指して~」
東日本大震災で被害を受けた商業高校生が開発した商品と本校の校章入り煎餅をチャレンジショップやイベントで販売。 |
| 平成25年度 全国大会出場 千葉県 |
「スマイル×幸せ×酒の華 ~地域に家庭に笑顔を咲かせよう~」
出張に来た人をターゲットに、大吟醸の酒粕と白い卵を使ったパウンドケーキを新潟駅やふるさと村で販売。 |
| 平成26年度 全国大会出場 北海道 |
「芝three(サン)芝show(ショー)~しばたにLOVE”-“LOVE”の景色を~」
パワーリーフを使ったどら焼きとパスタの販売、ランチの提供。
JA主催の大会にも出場し、東日本大会優勝、全国大会出場。 |
| 平成27年度 全国大会出場 青森県 |
「Three Eyes ~3Mプロジェクトで WIN-WIN-WIN~」
市場に流通しない野菜を使ったアイスクリームをイベントで販売。また、小学校の給食に導入される。 |
| 平成28年度 全国大会出場 宮崎県 |
「Link ~ここにしかないインバウンド観光への挑戦~」
台湾からの旅行客3,000人を目指し、お土産と繁体字による観光マップを作成。新発田市民に台湾のスイーツ「豆花(トウファ)」を販売。 |
| 平成29年度 全国大会出場 長野県 |
「Sustainable ~つくる・つなぐ人・たべる人がフェアトレードでハッピーに~」
フェアトレードの認知度を上げるためにフェアトレード製品と新発田麩、越後姫を使った焼き菓子、東ティモール産コーヒーの販売。 |