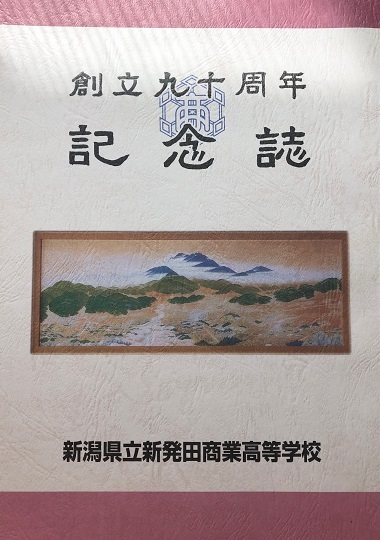
90周年記念誌を抜粋して紹介します
大切な伝統を守りつつ、新しい歴史を作っていこう

県立新発田商業高等学校が創立されてから、90年という歳月が経過しました。年輪を重ねる事90年・・・。改めてその歴史の重さを感じざるを得ません。こんな想いを胸に、このたび創立90周年の記念事業の一環として記念誌を発行するにあたり、一言ご挨拶申し上げます。
現新発田市民文化会館の地にに、大正6年に町立新発田田商業学校として開校以来、新発田商業高校は、幾多の変遷を経て、今日本日に至りました。昭和5年には水原新道の新校舎へ移転、太平洋戦争の真っ只なか、昭和19年には新発田工業学校となり、終戦を迎えました。戦後の経済復興に必死で取り組む中、昭和23年に商業、土木、建築の各1学級が設置され、新発田商工高等学校と改称されました。その後、戦後の復興も急速に進み、昭和39年には日本はオリンピックを開催するまでに驚異的な発展を成し遂げました。県高校教育の基盤も整備され、年を追って母校も校地の拡張、教室の増築、学級増がなされていきました。ここに至って商工分離の機運が高まり、同窓会役員、市当局、関係者のご努力により、昭和58年、新生、新発田商業高等学校として、新築移転され、現在に至っております。
この間、歴史と伝統に育まれた多くの優れた人材が、県内はもちろん、全国各地でめざましい活躍をされています。長い歴史の中では、全国制覇を成し遂げたクラブもあり、運動部、文化部ともに全国に「芝商」の名を知らしめてくれました。この伝統は、めんめんと現在も部活動に引き継がれております。
時代が変わっても、母校がある限り、この良き伝統が継承されて、いつまでも誇れる芝商であり続けることを願うものであります。
記念誌の発行が同窓の絆をさらに深める一助となれば幸いと思いつつ、90周年事業の実施にあたり、ご尽力を賜りました多くの皆さま、ご寄稿いただきました方々に厚く御礼を申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。
同窓会長 嶋谷次郎八
回顧 昭和12年3月卒 大瀧さん
私の入学は、昭和7年で、三の丸校舎から現在の南高校の場所へ移転して間もない新しい校舎でした。当時は水原新道と呼ばれた町はずれで、大きな建物は農業学校と2つくらいしかなかったと思います。校舎の西裏側に町裏練兵場(現在は大栄町の住宅)があり、その頃、満州事変や日支事変などがあったので、正規の授業の中で軍事教練が組まれ、巻脚絆を付けて三八式歩兵銃を担いで場内を走らされたものです。
練兵場の片隅に小高い山があり、その頂上に、昔使った小さな大砲が据えられていて、雨の日も風の日も毎日町役場の職員が来て、その大砲にぼろきれと火薬を詰めて発火させ、ドーンと大きな音を出して、町中の人に正午を知らせたものです。私たちはこの山を「ドン山」と呼んでいました。
最近の我が母校も県大会、全国大会で活躍していて、心強く感じています。校舎前の垂れ幕が毎年増えていくことを祈念しています。
母校 創立90周年に寄せて 昭和43年卒 和田さん
商工の3年間は、珠算部に所属し、田辺先生の指導の下で練習の日々を過ごしていました。春、夏、冬休みも朝早くから学校に通い、読み上げ算、暗算、実務問題の計算と練習に明け暮れました。ですから、同級生と親しく会話をしたり遊んだりしたのは、3年生の2学期になってからでした。
昭和58年4月に県立新発田柴田商業高校が開校を迎え、開校式は昭和58年10月29日、盛大に体育館で挙行されましたが、そこに、開校に尽力されました初代 故高橋庄吉校長先生の姿を見ることはできませんでした。校長先生の教育方針である鶴翁訓「一事専念 堅忍不抜」の教えが、生徒一人一人に伝わり育っていると思います。
創立80周年記念には、芝商の発祥の地である新発田文化会館前に記念碑を建立し、歴史を重ねてきました。今回も思うことですが、同窓会の先輩方は本当に母校を思い、支えていきたいという気持ちが強いと感じました。
後輩の皆さんが大会で活躍され、テレビや新聞等でメインに取り上げられると頼もしく思います。これからも母校の益々のご活躍と同窓会のご健勝を心から祈念申し上げます。
貴重な時間 平成2年度情報処理科卒 小林さん
世に言うバブル期真っ盛りの昭和62年に、高校進学を控えていた私に新発田商業高校に情報処理科が創設されるとの情報が入ってきました。今でこそIT社会で社会的ニーズの高い職種となっていますが、当時はよくわからず、なんとなく志望したように記憶しています。今思えば、私を含めた情報処理科の一期生の同級生たちは、新しいもの好きのミーハー集団だったのかもしれません(同級生尾みなさんごめんなさい)。
まず高校に入学して我々が目指したのは、情報処理技術者試験の第2種と呼ばれる国家資格です。
担任の古田先生、副担任の古西先生をはじめとする情報処理科の先生方は相当気合が入っており、専門学校並みの進路でスパルタ教育が展開されていきます。
古田先生から「諸君たちには無限の可能性がある」と叱咤激励されながら勉強に励みましたが、今でも、IT音痴の私はちんぷんかんぷんで、目標を達成することができませんでした(出来が悪くてすみませんでした)。
しかし、夏休み返上で暑い教室で勉強したこともあり、2年生の秋にクラスから見事に10名の合格者が出て、卒業までに述べ13名の合格者が出たように記憶しています。ここで得た知識や技術を生かし、現在多くの同級生が第一線で活躍しています。
また、情報処理検定のみならず簿記検定についてもチャレンジさせてもらいました。私はこちらの方が性に合っていたようで、今では税理士として仕事をさせていただいているということを考えると、高校時代に学んだことから将来の道が決まり、運命的な学習をさせていただいたと、今改めて思うところです。
また、個人的に忘れられないのが柔道部の思い出です。初めの関門は坊主頭でした。勧誘時には自主的なものと聞いていたため、全員が坊主頭の先輩方は変人揃いぐらいに思っていた私は、自分が甘かったとすぐに気づかされました。結局は多方面からの強い指導があり、観念して断髪式を行うことになりました。次の関門は先輩方からの暖かいご指導です。当時の柔道部は先輩方からの命令は絶対服従でした。無理難題が飛び交い困惑しましたが、社会人となった今では世間の荒波に比べたらまだマシであり、良き社会勉強の一環であったと思います。
最後の関門はなんといっても顧問の富所先生です。怖いなんてものじゃありません。たかだか十数年しか生きていない我々には抗弁の余地もなく、3年生の最後の大会が終わるまで常に恐れながら稽古を積んだものです。思い起こしても生涯の中で、あれほど怒られたこともないでしょう。しかし、全て我々を思っての教育であり、家庭も顧みずに日曜や夏冬休みの全てにお付き合いいただいた先生には感謝の念がつきません。
最後になりますが、すべてにおいて現在の基礎が育まれた高校生活は、私にとって、とても貴重な時間でありました。母校、新発田商業高校のご発展を心より祈念する次第です。
芝商3年間 平成15年度商業科卒 新村さん
商業高校に入った理由は、将来のために自分の身になる能力や資格を取りたかったことと、小学校から続けてきたバレーボールを続けて全国大会で勝ち進む実力をつけたかったためです。
まず、私の前に立ちふさがったのは、未知の世界の「簿記」でした。中学校で勉強してきた知識は全く通用するどころか、使う場面がないのではと思うほど分かりませんでした。スタートラインはみんなと一緒なのに、計算が苦手な私はどんどん置いていかれた気がしました。見たことのない単語や計算式、何冊もある教科書に内心ついていけないかもと思いながら、必死になって先生の話に耳を傾けました。
「簿記」は私にとって大きな難関でしたが、努力して勉強した甲斐があって、なんとか念願の資格を取得できたときは本当に嬉しくて飛び上がって喜んでいたことを覚えています。
そして資格取得だけではなく、私が勉強を頑張れた理由にはやはり部活動がありました。バレー部の一日は朝早く、夜遅くという生活で、勉強も時間が空いているときに集中してやらないと睡眠時間がなくなってしまいます。自分で希望してこの生活を選びましたが、勉強時間の少なさや遊び時間のなさに何度も周りの人をうらやましいと思ったことがありました。でも、その反面、私たちにしか味わえないことは数えきれないほどたくさんあり、ほとんどの時間をバレーボールに費やしてきましたが、1日も後悔したことはありません。
私たちは毎日汗でビショビショになりながら、全員で厳しい練習をしてきました。上下関係や部活の規則など、決して甘いものではありませんが、お互いに励まし合い、時には全力でぶつかりながら目標を達成するために、日々努力してきました。その結果、何年ぶりかの全国大会1回戦突破を果たすことができ、本当に嬉しくて、みんなで泣いて喜んでいたことを今でも鮮明に思い出します。
3年間、今考えると、とても多忙な毎日を送っていましたが、この高校生活で大きく成長することができたと思います。
芝商に感謝 旧職員 沼沢輝雄
私は、昭和37年芝商商業科に入学、関川村から通学していたので、朝5時起床、帰宅は8時を過ぎていましたが、憧れの芝商でしたので苦になりませんでした。進路は就職を考えていましたが、担任の本間重蔵先生の薦めもあり、新聞配達をしながら大学で学ぶことを決めました。
大学卒業後、第11代校長、阿部 博氏に声をかけていただき、母校の定時制に採用されました。旧校舎の正面玄関の2階で職員室でした。生徒は日中働いていて、疲れも見せずに勉強していました。授業を終えても、クラブ活動や生徒会の仕事を夜遅くまで楽しくやっていました。日曜日は生徒と一緒に二王子岳や五頭山に上りました。生徒に対しては、後輩だという思いもあり、勉強を教えるというより共に生活をしたという5年間でした。
商工分離から2年後に、再び芝商にお世話になりました。分離5周年と創立70周年記念事業の準備と同窓会の仕事をやらせてもらいました。角界で活躍されている先輩方と仕事ができ、大変心強く思いましたし、多くのことを学びました。年1回の東京同窓会に同窓会長と学校長と共に招かれ、酒を飲み交わしながらの話に感激したものです。ホテルのオーナー、公認会計士や社長、専務と各方面で活躍されている方がなんと多いことか。その中でも、ひときわ目を引いたのは、時津風親方(元大関豊山)でした。私が高校2年生の時、大関に昇進され、体育館で後援会から「化粧まわし」の贈呈式があり、感激したことを今でも覚えています。若貴兄弟の兄の若ノ花が横綱昇進の報告を受けた時の返礼の口上に、「堅忍不抜」の言葉を使っていました。この言葉は芝商の校訓になっているもので、当時の理事長時津風親方からの導きがあったのではないかと、私は勝手な想像をしてひとり喜んだものです。
高校の同級生でバレー全国大会ベスト8の名セッター川口氏が手弁当で女子バレー部を毎日のように指導しておりました。私は、バレーは全く素人でしたが、誰かが彼をバックアップしなければという思いで同級生のよしみもあり、顧問を引き受けました。川口氏は大会の時はいつも泊まり込みで来てくれました。奥様も選手に差し入れを持って一緒に応援してくださり、県ベスト4まで選手を導いてくれました。残念なことに3年前に奥様が亡くなられ、後を追うように川口氏も次の年に亡くなりました。2人のことは決して忘れることはできません。
その後、佐藤孝先生が赴任され、女子バレー部監督に就任。先生は絶対にこの選手たちを全国大会に連れて行きたいと決意され、厳しく選手を鍛えていました。選手は苦しかったと思いますが、よく耐えて応えてくれました。素晴らしい保護者のバックアップもあり、平成10年に全国大会(春高)に県代表として出場することができました。私もその中の一員に加えさせていただき、感動することができました。
私は今年の3月で定年退職をしましたが、これまでの人生の三分の一をこの場所で過ごしてきました。素晴らしい生徒と職員、保護者、同窓の先輩方に出会うことができ、心温まる感動の日々を過ごすことができました。皆さん、本当にありがとうございました。
記念講演会 「負けてたまるか」~努力は人を裏切らない~
元三和銀行(現三菱東京UFJ銀行 大久保支店長)
現株式会社エイエヌオフセット専務取締役
商工第10回(昭和35年3月)卒業 荒井 一男 氏
皆さん、創立90周年おめでとうございます。35年卒業生の荒井一男と申します。私は、47年前に、今は三菱東京UFJ銀行となっていますが芝商より初めて三和銀行に入りました。
大きな組織で、高卒というハンデを「負けてたまるか」という気概で頑張り、高卒では極めて稀な4カ所の支店長を経験しました。私の後、後輩が30人近く三和銀行に入社し、新発田商業が一大勢力を築きました。
55歳で銀行を定年退職し、現在はエイエヌオフセットという総合印刷業に入りました。異なる業界でも負けてたまるかという気持ちで頑張っており、いま66歳ですが、まだまだ若い連中には負けないぞという気概で頑張っています。
高校は、父の教えを守って新発田商工へ入りました。当時、高校は一学年に商業が3クラスありました。1クラスは55人でした。女性は20%で、私たちのクラスにも10人くらいいました。あと、建築と土木がそれぞれ1クラスずつの5クラスです。
私は商工に入ったとき、第四銀行に入りたいと思っていましたので、簿記と珠算とともに、1級を2年生の時に取るという目標を立て、クラブは珠算部に入りました。小学校4年生の時に3級を取得したっきりで、その後はやっていませんでしたので、珠算部に入りました。田辺武司先生は、今でも珠算部の顧問をされており、非常に熱心で、ガリ版で問題集を作って部員に問題をやらせました。ただ、大変厳しい方で、正月以外は休みなしでした。私も何度かやめようと思ったのですが、やめたらだめだと思って一生懸命取り組みました。
先輩にも優秀な方がいましたが、後輩にもどんどん優秀な方が入ってきましたので、私が入部した32年から全国大会に出ました。先生から先日ご連絡をいただいたのですが、今年も全国大会で入賞したそうですね。50年連続出場していますが、こういう学校は日本広しといえども、新発田商業と大阪の天王寺商業の2校だけだそうです。
続けることは大変体力がいりますし、ひとえに田辺先生の熱心の表れだと思っています。私もここで3年間頑張ったおかげで、銀行に入ってから非常に力になりました。継続は力ということを本当に体感しました。
当時の銀行は非常に権威を持っていて、企業が運転資金や設備資金が必要なときは、銀行借入が主でした。今のように社債を発行したり、株を時価発行したりする時代ではなかったため、銀行依存が非常に高かったのです。銀行もむやみやたらにお金を貸しませんでした。日本銀行の貸し出し枠規制があり、企業が必要とする資金の6,7割しか出せませんでした。企業の銀行詣でが非常に盛んで、支店長を頻繁に料亭で接待している時代です。赤坂や向島が繁盛していた時代で、芸者さんもいました。私たちも入社してから4,5年たつと、小唄を習わせられました。
大阪で入行式を行い、35年には高卒が200人、北は北海道、南は九州鹿児島からたくさん集まっています。新潟からは高田商業や長岡商業の方もいました。それから、大卒が100人。東大、京大、一橋、阪大、神戸大、慶応、早稲田の一流どころがずらりと並んでいます。女子は大阪だけで300人という時代です。
2週間の研修を終えて、いよいよ配属されました。私は東京の日本橋にある室町支店という店に入りました。ここはすぐ前が日銀の本店や三越の本店があるところです。室町支店というのは旧山口銀行の東京支店ということで名門店で、都内でも一番か二番に大きなお店です。大卒の優秀な人が毎年入っているのですが、高卒は非常に肩身が狭い状況です。私と一緒に入った大卒2人も東大卒と慶応卒です。慶応の方は最後には副頭取までやりました。
最初は内部の仕事をするわけです。出納係として、大きな現金を数えたり、手形や小切手を持ち出したりします。そのあと、普通預金や定期預金です。当時はパソコンのない時代だったので、そろばんが主流でした。そこで私のそろばんの腕前が活かされ、3年間田辺先生に教えを受けた成果が出ました。
手形でも小切手でも持ち出すのもわけないものですから、みんな見に来て「早いな」と感心していました。三和銀行の中で、珠算大会と定期預金の大会がありました。その秋に珠算大会に出たら三和一になり、人事部に注目されました。芸は身を助けるということだろうと思います。毎年上位入賞し、4年目には定期預金係になっていましたので、定期預金の大会に出て3位になりました。
自分の夢に向かってどうするのか、目標は支店長になりたいということです。当時、学歴は出世の予約表ですから、一流大学を出た連中がたくさんいる中で、支店長になれるのか、目標を次長ぐらいに格下げしようと思ったのですが、親父の反対を振り切ってきたのだから、やはり支店長を狙おうと思いました。負けないためにはどうするか、仕事で勝つしかないと思いました。人間的な魅力も含めて、総合力で勝とうと思いました。
しかし、まともな戦いでは駄目だと思いました。勝つためにはどんなことをしたらいいのか、人の3倍努力しようと本当にそう思いました。優秀な人でも努力します。私のような平凡なやつが優秀な人に勝つには、3倍努力しないといけない。2倍ではダメだなと思いました。
人の3倍努力するということが1つ目で、2つ目は目立つためには人の嫌がる仕事をやろうということです。レクリエーション委員や旅行幹事、従業員組合の仕事、それから勘定が合わない時には率先して出て行って勘定を合わせるような仕事をしました。囲碁も覚えて、得意先との囲碁の会の幹事の仕事も積極的にやりました。この2つは入行した年に考えたのですが、3年たってある大きな挫折があった後に私が考え直したのは、友人は財産、友達は財産ということです。良い友達を持って、そこからいろいろなものを吸収していこうと思いました。主任になってからは、もうひとつ上の立場の気持ちになって仕事をしようと考えました。そうすると全体が見えるし、いい仕事ができると思いました。この4つを28,9歳くらいまでに考えました。
内部の仕事も4年目で預金主任をやって中心になりました。勘定が合わないとき、真っ先に出て行って勘定をこべしました。「こべる」という言葉は勘定を精査するという銀行用語です。銀行用語にも面白い言葉がありまして、一つ二つご紹介しますと、入ってすぐに女性から「荒井さん、だいてください」「え?」「荒井さん、だいてくださいよ。」私が真っ赤になりましたら、「荒井さんは誤解しているんじゃないの?代金取立手形、遠隔地の手形小切手を取り立てに回すことを代金取立手形、代手と短縮しているんですよ。」と言われました。それから「荒井さん、手形落ちてる?」「どこに落ちているの?」違うのですね。この手形が決済できたかどうか確認することを「落ちた」と言います。銀行の専門用語はたくさんあります。
勘定が合わない時の合わせ方もいろいろあり、代表的なのが三つあります。桁違いと逆転数字、それから出入りの逆記帳です。まず9で割るんです。割れたら桁違いか逆転数字。例えば、3600円が合わないとするでしょう。9で割ると400です。4という数字です。そうすると4000と400の桁違いで3600になるわけです。例えば7200が合わなかったら、9で割ると800です。800と8000の桁違いだなと。
逆転数字はやはり9で割って、3600ですと400です。2桁の数字が差額4の逆転数字ですから、4だと1と5。1500と5100。これで3600になります。あるいは2と6。2600と6200の逆転数字ですか。
そういうふうにして調べると大体出てきます。二重記帳というのは、出と入りを逆記帳しますから、2で割ると、4000合わないと言ったら、2000の数字を、出が大だったら、入りの伝票を出で打っているというのが2000です。そんな形で調べました。
入行後、順調に進んだように思えますが、実は非常に大きな挫折がありました。入行して1年ちょっとたったころに、無理が重なり、体調を崩して数か月休みました。張り切って頑張っていたのにショックでした。目一杯頑張ってきたゴムが切れたのでしょうね。栄養失調もあったと思います。それまでは「所詮、一人」だと思っていたのですが、自分だけの力ではダメだと思うようになりました。先輩から「お前は真面目すぎる」「もう少し肩の力を抜いて周りを見なさい」「に向かって勉強ばかりしていてもダメだ。優秀な先輩や同僚を友達として、そこから良いものを取りなさい」と言われました。同僚の女性からは、「荒井さんは一生懸命やっていて、近づくのが怖いぐらいだったわ」と言われました。ショックでした。自分を見直す良い機会だと思い、従来の勉強もやりますが、6,70%ぐらいに落として、積極的に友達、先輩を作ろうということで、復職した後積極的に会合に出たり、友達と飲み食いをしました。
新橋支店で3つの大きな変化を体験できました。結婚しました。5月31日に新発田で見合いをしました。それが家内です。芝商の出身で、第四銀行に入っていました。
それから新橋支店の責任者になりました。支店長代理になったのですが、39年の大卒トップクラスと同じになりました。それから二年後に父親になりました。その後、東京業務本部で審査の仕事をやったり、渋谷支店で貸付代理や取引先代理を務めました。この時期、私は組合の東京支部長を務めました。銀行の場合、従業員組合の役員をやると、結構出世コースに乗ります。私も出世コースの端くれに乗ったのかなと思いました。
四谷支店の営業課長を務め、越谷で次長を務めた際、二つ目のチャンスが巡ってきました。支店長は海外帰りであまり国内のことを知らなかったので、私が仕切ることが多かったのですが、郊外店の銀行は、夏のボーナスと冬のボーナスで、ボーナス預金を集めるのが一つの仕事です。7月に成績の悪い支店に、東京業務本部長の佐藤専務という支店統括ナンバーワンで、預金の神様と言われた方から電話が入りました。その専務から電話がかかってきまして、「支店長はどうしている」「今お中元を配っていますよ。次長の荒井でございます」「ボーナス預金、悪いじゃないか」「佐藤専務、ご心配をおかけしてすみませんが、越谷あたりは8月にボーナスが出るので、絶対にやりますからご安心ください。ご心配なく」と言ったら、「えっ?」ちょっとびっくりされました。それまで数か所の支店長に電話をしたら、ちんぷんかんぷんの支店長が多くて、次長ごときが「大丈夫、お任せください」と言ったものだから、びっくりなさったのです。この男はどういう男だと、矢継ぎ早に質問をされて30分ぐらい話しました。
その2か月後に支店部の企画担当の次長になりました。受け答えが悪かったら、多分ダメだったのでしょう。これで支店長への道が開けました。ここは大卒の重要なポストで、支店長会の資料を作ったり、専務の原稿を書いたりする支店部長の大事なブレーンの一人です。従来大卒の優秀な人がやっていたので不安だったのですが、ここでも、「負けてたまるか」、「人にできて自分にできないはずはない」ということで、一生懸命にやりました。
計数を総括するところですから、ここでも珠算部の経験が活きました。珠算をやることは計算が強くなるということだけではなく、数字に対する概念も強くなります。数字は荒井に聞けと言われるようになりました。そして、2年後に支店長になりました。支店長の面白さは、支店の雰囲気をガラッと変えられることです。それから、部下との共存です。部下をいかに使い、一緒にやるか、いかに気持ちよく働いてもらうかが共存共栄です。
私は、モットーとして、支店の成績を上げることが50%、部下を育成することが50%でやっていこうと思いました。
4か所の支店長を務めましたが、スローガンとしては、遊びも仕事も一生懸命やろうじゃないか、仕事だけじゃない。それから支店全員は家族だよ。お互いに助け合おうじゃないか。その代わり厳しいことも言うよ。そっぽを向いた人がいたら、厳しいことを言ってこっちに向かせます。運命共同体ですよという姿勢でやりました。攻めと守りをバランスよくやろう。業績と義務のバランスをよく取りましょうと。
最後になりますが、生徒の皆さん、ぜひ目標を持って社会人になってください。負けてたまるかという気持ちでいれば、いろいろな解決策が見いだせてきます。そこでぜひ頑張っていただきたいと思います。「努力は人を裏切りません」チャンスは3度きます。そのチャンスをぜひ捉えていただきたいです。それから良い友達を持ってください。そのためには、自分も良い友達になるために頑張ることを心がけてください。それから、感謝の気持ちを忘れてはいけません。
人間は、自分一人では生きていけません。人間は自分一人では成り立ちません。周りの人とのいろいろな関係があって生きているのです。感謝の気持ちを忘れずにいてください。社会人になって最初の給料をもらったら、お世話になった親や先生、そういった人たちに靴下などの特別ではないもので結構ですから、贈ってほしいと思います。こういう気持ちを忘れないでいただきたいと思います。